「私でもできる感染制御への関わり」
大阪市保健衛生検査所 堂園 昌隆
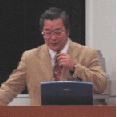
去る2月22日(火),大阪市立大学医学部4階中講義室において大阪大学医学部附属病院感染制御部 浅利 誠志 先生をお迎えして,「私でもできる感染制御への関わり」と題して御講演頂きました。以下に,当日の講演内容について報告致します。
(感染症法やCDC勧告の矛盾点)
1.患者の隔離について
※一類感染症を除いて,隔離を最も急ぐ感染症とは何か?
隔離を最も急ぐ感染症は麻疹・水痘・結核・インフルエンザであり,赤痢・チフス・コレラなどの接触伝播の感染症では患者の隔離を急ぐ必要はない。
二類感染症(赤痢・チフス・コレラ)は隔離することになっているが,感染経路予防策が徹底していれば隔離をする必要はない。赤痢やコレラ患者を隔離しているのは日本だけである。
2.術前手洗いの常識について
※病院手術場の滅菌水と水道水ではどちらが清潔か?
※術前手指消毒に水道水を使ってはならないのか?
管理されていれば水道水でも逆浸透膜ろ過装置(RO水)やろ過滅菌水でも細菌数に有意差は無い。管理されていないRO処理水よりもむしろ,1分以上流した水道水の方が清潔である。その上,ろ過装置ではUV殺菌灯や除菌フィルターなど高額なメンテナンス費用もかかる。
厚生労働省より医療施行規則の一部改正(H17.2.1)がされた。改正の要点:水道水及び滅菌水による手洗いに有意差が認められないことから,術前手指 消毒に滅菌水の使用は必須ではないとなった。
3.術前検査について
※術前検査をどの範囲まで行うか?
日本では手術前検査料金はトータルで1310点しかなく,基礎疾患管理に必要な検査料金を差し引くと殆ど残らない。残った点数でHIVやHBVなどの術前検査をどこまでできるかといった現状であり,CDCのガイドラインとは乖離した状況にある。
感染症背景の違う日本で同じCDCマニュアルは使えない部分がある。また,病院内での感染症マニュアルは診療科によって背景が異なるため一部を変える工夫が必要である。
(感染制御の目的)
ICTの本来の目的は,感染症で死亡する患者を無くすことであるにもかかわらず,日本ではいつの間にかサーベイランスをすることが中心になっている。
米国では感染症対策に人・物・金を大量に投じてきたにもかかわらず,なぜ耐性菌が減少しなかったのか?
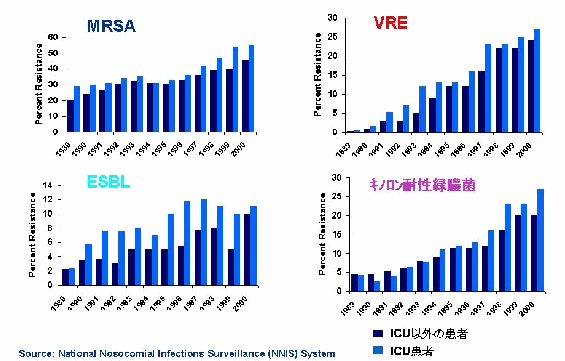
図1 米国における耐性菌の年次推移
その原因として,次のようなことが考えられる。
○ 接触感染予防ができていない
CDCではMRSAやVREは環境から伝播はしないとしている。しかし,滅菌手袋を着用後MRSA保菌患者の病室に入室し,患者に全く触れずに環境(ベッドの柵,テーブルなど)との接触で40%の手袋が汚染されていたという調査結果も2003年に出ており,MRSAが環境から密接に伝播していることが証明されている。
○ 監視培養の軽視
手術予定の患者で基礎疾患が重篤な場合は,手術前にMRSAの監視培養を行い陽性の場合は除菌することが術後感染症の頻度を低減化させる。特にコントロール不良な糖尿病の患者が直腸癌の手術を行うケースや臓器移植患者では監視培養と除菌が重要である。しかし,術前のMRSA保菌検索は保険診療では認められていないため,監視培養の徹底にも診療報酬上の大きな問題が生じている。
○ 医療器具・機器の汚染調査
前述の手術室の滅菌水の他にも,耳鼻科で使う舌電極や気管支ファイバーなどはラボ(微生物検査室)で汚染調査すべきである。このような活動によって感染制御に果たす検査室の役割が病院職員に認識される。
○ 個人認識の甘さ
人は監視されないと行動変化を起こさない。逆に監視カメラがあるとそれだけで人の行動は変化する(ホーソン効果)。
感染症サーベイランスを実施するには,点を捉えるスポットサーベイランスではなく基本的に線や面を捉えるための継続的な全サーベイランスを実施しなければならない。しかし,1,000床の病院で8名のICPを置いている米国ですら全サーベイランスに失敗しているのが現状である。ましてや,1,000床の病院でICPを兼任で1名しか置いていないような日本では,スポットサーベイランスが限界である。
また,感染症治療学と感染制御学とは違うものである。日本で感染症対策を推進しているのに徹底されていない理由は感染制御学の知識があまりに乏しいためである。
(検査室として何をすべきか)
"検査技師だから検査のことしかしません, 知りません"では駄目である。これからの高度先進医療を支える検査技師は,菌の情報とそれに用いるべき薬剤の情報,現在使っている薬剤の適否も含めた情報を判断・提供できるように努力すべきである。これからの感染対策・治療においては,医師だから,薬剤師だからという垣根は無くチーム医療としての協力体制を構築していかなければならない。
更に,各診療科に適した薬剤サイクリングの相談にも対応していけるだけの知識を持ち,臨床医や薬剤師への適切なアドバイスができるようにならないと・・・検査をしているだけでは検査室は必要とされなくなる。また,臨床の場で,耐性菌を決定するのも,耐性菌をどうように治療するかを決定するのも検査室であるといって過言ではない。
LBS(ラボラトリー・ベースド・サーベイランス)
我々は,普段の検査業務の中で血液や髄液など本来無菌的な材料が陽性になればグラム染色で確認後,その菌に有効な薬剤まで考えている。また,このような検査室でしか出せない情報によりアウトブレイクの兆候を察知することも可能である。院内感染の兆候はラボが一番先に気づくことであり,検査室が一番早く警鐘を出せるのである。
但し,これらの情報は主治医への提供だけで終わるのではなく一症例毎にその迅速塗抹結果をICTに報告するという流れにしなければならない。さらに,耐性菌情報をまとめICTの機関誌などを通じてタイムリーに職員に伝達しなければならない。検査室はいくらでも感染制御に関与できるし,関与していかなければ感染対策の徹底は困難である。
但し,微生物検査の改善やサービス向上をおろそかにして病院の感染制御体制の不備を論ずるのは言語道断である。例えば塗抹検鏡結果においても,見えている菌の情報の提供だけでなく菌が見えていなくても,多核白血球やリンパ球などの背景細胞成分から急性期・慢性期,細胞内・細胞外寄生感染症などまで読めるようにならなければならない。
(感染制御を推進するにあたって)
新たな感染対策を病院職員に推進する場合,同時期に複数の対策を勧めるのは好ましくない。例えば手洗いひとつでも,数千人の職員が勤務している病院内ではひとつの行為を改善するのに数千人の職員全員が改善していくことになる。4つも5つも同時に変更すると職員の感染対策の意識が薄れ,感染対策は感染制御部が勝手にやるものだという意識が生じてしまう。このため,ひとつの新たな対策を実施した場合は,その効果を検証することを忘れてはならない。マスクの配布,手洗い徹底,アルコール消毒綿花の市販品購入など,各自の施設で比較的スムーズに導入できることを1から始め検証していく事が感染症制御の成功の近道である。CDCのマニュアルの日本語版を購入しても読みきり,使いこなさなければ意味はない。
(講演の感想)
感染制御の色々な事象を講師とフロアーとの質疑形式で解説して頂き,非常に有意義で印象に残る御講演でした。
私の勤務する施設でもこれまでに検査業務のみならず,医療監視や保健事業の評価など様々な分野に検査技師が進出しておりますが,感染制御の分野においても"必要とされる検査室"となるために,どのように,どこから取り組むか,その糸口が見えたように思います。
[用語和訳]
Infection clinical nurse specialist:感染専門看護師
Infection control and prevention:感染制御
Infection control committee:感染対策委員会,院内感染対策委員会,病院感染対策委員会
Infection control doctor ICD:感染管理(制御)医師
Infection control nurse ICN:感染管理(制御)看護師
Infection control practitioner ICP:感染管理担当者,感染制御専門家
Infection control team ICT:感染対策チーム,感染制御チーム
Infection surveillance:感染症サーベイランス
Infection-control programs:感染制御プログラム