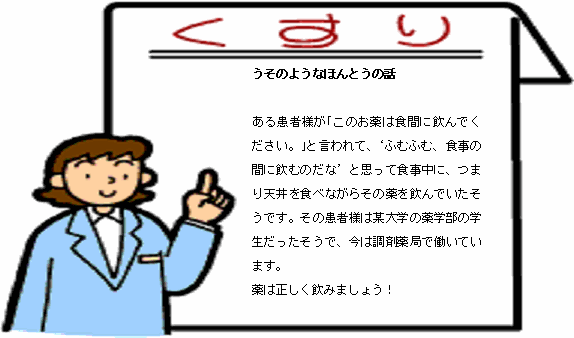感染症検査と臨床に役立つ抗菌薬情報と投与方法
-耐性菌を中心に-
大阪第二警察病院 池田 千賀子
去る平成16年11月30日(火)に,萬有製薬株式会社 市販後臨床開発推進部 松田耕二先生をお迎えし,「感染症検査と臨床に役立つ抗菌薬情報と投与方法 -耐性菌を中心に-」と題しまして大変詳細なご講演をしていただきました。以下にご講演内容を報告させていただきます。
〈臨床現場で問題となっている耐性菌〉
・ MRSA
・ PRSP,PISP
・ VRE
・ ESBL産生菌(大腸菌,肺炎桿菌など)
・ メタロ-βラクタマーゼ産生菌(緑膿菌,セラチア)
・ BLNAR,BLPACR,BLP
など
〈耐性の機序〉
・薬剤を分解する:β-ラクタマーゼによるペニシリン,セフェム薬の不活化,メタロ-βラクタマーゼによるカルバペネム薬の分解など
・薬剤を修飾して失活:修飾酵素によるアミノグリコシドの失活,クロラルフェニコールアセチルトランスフェナーゼによるクロラムフェニコールの失活など
・透過性の変化:ポーリン蛋白質の減少(透過孔の減少)による薬剤透過性の低下,薬剤排出ポンプによるテトラサイクリン,キノロン,β-ラクタム薬の耐性など
・標的部位の質的変化:MRSAにおけるPBP'2の産生,VREにおけるD-ala-D-lactateまたはD-ala-D-serineの産生,PRSP,BLNARにおけるPBPの変異など
〈ESBL感染症の治療〉
・ ESBLが起炎菌であることの的確な診断
・ β-ラクタマーゼ阻害剤
・ セファマイシン系薬
・ カルバペネム薬
〈メタロ-βラクタマーゼ保有菌が見つかったら〉
-メタロ-βラクタマーゼは最強の破壊兵器-
・ すぐに医師に報告する!!
・ 院内感染対策を厳重にする
・ 完全に殺菌する(体内,体外)
・ 環境の消毒
・ 治療はβ―ラクタム以外を考慮する
〈緑膿菌の薬剤耐性〉
・ 抗菌薬不活化による耐性
・ 標的部位の変化による耐性
・ 外膜透過性による耐性
・ 薬剤排出機構による耐性
・ バイオフィルムによる耐性
〈緑膿菌感染症に対する併用療法〉
・ 作用機序,作用点の違うものを組み合わせる
・ 殺菌力の強い方を先に投与する
・ 殺菌力が同じものは同時投与
〈抗緑膿菌活性まとめ〉
・ GMは分子量が最小のためカルバペネム特異的ポーリンを通過しやすい。
・ 排出蛋白の基質にならない
・ 初期殺菌能が優れている
〈MRSA感染症治療の要点〉
・ 発症例と定着例の区別
発症例:早期から抗MRSA薬の全身投与
定着例:消毒剤による局所治療
・ 体腔内異物の除去(カテーテルなど)
・ 膿瘍の穿刺/切開排膿
・ 複数感染症に注意
・ 抗MRSA薬の投与
1. VCM,ABK,ST合剤,MINO,REF(単剤投与は耐性化するのでNG)など
2. 症状の軽快が目標
3. 副作用に注意
〈BIVR感染症の危惧〉
BIVRとは ・・・ バンコマイシンとβ-ラクタム薬の併用で拮抗現象を起こすMRSA(VCMヘテロ耐性黄色ブドウ球菌
VCM8μ/ml ・・・ 細菌学的には耐性,BIVRであるMu-3のMICはβ-ラクタム剤存在下で8μ/ml。臨床的には耐性,VCMの組織移行は喀痰で2~3μ/ml,肺炎時のVCMブレイクポイントは2μ/ml。VCMの殺菌力は弱い
BIVRの検出法 ・・・
1. TSBで一夜培養した菌液をOD578nmで0.3に調整する
2. VCM4μ/mlを含むBHIA plateを用意する
3. VCM plateに試験菌を綿棒で塗抹する
4. β-ラクタム剤含有(濃度は1~100μ/ml)8φnm paperdiskを置く
5. 37℃で20時間培養し,β-ラクタム剤によって耐性が誘導され,paperdiskの周りに生育帯ができれば,ヘテロVRSAとする
BIVRの耐性機序 ・・・ TEICはtrancepeptidaseのみを阻害するのに対し,VCMはtranspeptidazeとtransglycosidaseの両方を阻害するため,ムレインモノマーはVCMの方が多く遊離され,さらにβ-ラクタム薬で相乗的にムレインモノマーが遊離される。ムレインモノマーは細胞壁構築に再利用され,細胞壁が肥厚してVCM耐性となる。BIVRはMRSAwo長期間VCMに暴露することによって生じる。
BIVRの治療 ・・・ TEICとIPMの併用
〈PRSP感染症に対する化学療法〉
中耳炎 ・・・ β-lactam系経口薬の増量投与(AMPC,CDTR,FRPM)β-lactam系注射薬(PAPM,AMPC,CFPM)
肺炎・気管支炎 ・・・ 中耳炎に同じ
敗血症 ・・・ カルバペネム系,VCM
髄膜炎 ・・・ PAPM,VCM
〈インフルエンザ菌に対する治療〉
・ MICが2μg/ml以下であればABPCの静注
・ BLNAR,BLPACRを選択する経口セフェム系の乱用を控える
・ BLNAR,BLPACRに対してはCDTR,CFPNなど新しい経口セフェム,ニュ-キノロン
・ 肺炎例ではCTX,CTRX
・ 髄膜炎の初期治療はCTXとABPCの併用,ついでCTX,CTRX
〈治療に用いる抗菌薬の決定〉
-どの抗菌薬を選択するか?-
・ 推定起炎菌に対する抗菌力があること
・ 感染部位への優れた移行性があること
・ 安全性が高いこと
・ 基礎疾患・アレルギー等,患者の背景を考慮すること
〈なぜ抗菌薬治療が遷延するか〉
・ 不十分な投与量の選択
・ 誤った投与経路の選択
・ 不適切な抗菌薬の使用
・ 十分治療する前に治療を終える
・ 起炎菌に抗菌活性のない抗菌薬の選択
・ 誤った抗菌薬の組み合わせの選択
・ 外科処置をしなかった
・ 耐性菌の蔓延
・ 抗菌薬中止時期の見誤り
〈耐性菌制御のための12ステップ(CDC)〉
・ ワクチン投与:インフルエンザ-肺炎球菌ワクチン
・ カテーテル抜去:不必要なカテーテルを直ちに抜去
・ 培養検査実施:治療開始前の培養検査実施
・ 治癒のための治療:確実な治療(量-投与法-期間)
・ 専門家へのコンサルタント:感染症科・薬剤部へのコンサルタント
・ 耐性菌状況把握:耐性菌サーベイランス成績の確認
・ VCM過剰投与留意:CNS検出時での留意
・ 狭いスペクトルへの変更:原因菌判明後はより狭域なもの
・ 定着例には不使用:コロナイゼーションには不使用
・ 不明の場合は中止:感染症不確定であれば中止
・ 隔離などの徹底:隔離/接触感染防止策
・ 伝播阻止:手洗い/Standard precaution
〈まとめ〉
治療に役立つ抗菌薬を選択するためには,
① 起炎菌の確実な同定
② 正確な感受性検査
③ 耐性菌を正確に検出するための検査
④ 耐性菌であればその耐性機構を理解する
⑤ 薬剤の特性(時間依存性,濃度依存性,組織移行性,吸収・排泄率など)
⑥ を理解する
⑦ 疫学による感受性パターンの把握
⑧ 患者背景
などが必要になってくる。耐性菌が多種多様化していく中で,ただ薬剤感受性を実施して結果のみをを報告するのではなく,これらのことを十分理解した上で,より臨床に役立つ情報を提供していくことが重要であると思われる。