どうしてますか?どこまでしてますか?〜嫌気性菌感染症検査〜
大阪医療センタ− 佐子 肇
去る9月17日,(株)アズウエルにおいて,大垣市民病院 石郷 潮美 先生を講師にお迎えして,『嫌気性菌感染症検査』 と題して嫌気性菌感染症の検査のポイントを中心に御講演いただきましたので以下に報告いたします。
● 内因性及び外因性嫌気性菌とは
内因性嫌気性菌:人や動物の粘膜表面にある細菌叢の構成する嫌気性菌
外因性嫌気性菌:動物の皮膚粘膜以外の部位(土壌や泥)に存在する嫌気性菌
偏性嫌気性菌が関与を示唆する臨床所見
1. 膿,分泌物,穿刺液,喀痰,呼気などの悪臭
2. 粘膜に接する部位の感染症
3. 膿瘍形成,壊疽,壊死組織の感染
4. 病巣,あるいは臨床材料中にガスが存在する
5. アミノ配糖体系薬物,モノバクタム系薬物など偏性嫌気性菌全般に無効な抗菌薬の使用中に発生または増悪した感染症
6. 腸管手術後及び流産後の感染症
7. ガス壊疽,破傷風,ボツリヌス中毒
*上表の1〜7に示すような臨床所見が認められる場合には,常に偏性嫌気性菌の可能性を考慮して対処する。
*1〜6は内因性嫌気性菌が関与している。
Prevotera spp. Porphyromonas spp. Fusobacterium spp.Peptostreptococcus spp.
Veillonella spp. Bifidobacterium spp. Eubacterium spp. Propionibacterium spp.
Clostridium spp.など
*7は外因性嫌気性菌が関与
主にClostridium spp.
臨床検査室は主に内因性嫌気性菌を扱っている。
● 嫌気性菌が原因による疾患別分類
1) 粘膜上の内因性嫌気性菌が組織に侵入して発症する
慢性中耳炎,慢性副鼻腔炎,嚥下性肺炎など慢性化膿性感染症
2) 環境中(土壌など)の外因性嫌気性菌が組織に侵入して発症する
ガス壊疽,破傷風
3) 嫌気性菌が原因となる食中毒
ボツリヌス中毒,Clostridium perfringensによる食中毒
4) 嫌気性菌を中心とした正常細菌叢の乱れが原因となる疾患
歯周病,細菌性膣症
5) 嫌気性菌による院内感染症
Clostridium difficileによる偽膜性大腸炎,化学療法薬関連下痢症
● 嫌気性菌の存在を示唆する細菌学的所見
1. 検体のグラム染色標本で菌を認めるが,好気培養で菌の発育陰性の場合
2. 嫌気培養血液寒天培地上の集落及び特徴的な性状
黒色色素形成:Prevotella spp. Porphyromonas spp.
パンくず様集落:Fusobacterium nucleatum
二重溶血性:C.perfringens
遊走:C.tetani, C.septicum
スパイダ−様集落:Actinomyces israelii
3. GAM半流動高層培地の嫌気帯でのみ増殖が認められる場合
4. グラム染色標本上で特異的形態が観察される場合(推定同定)
・ 大きなグラム陽性桿菌( 芽胞 ):Clostridium spp.
・ 破傷風患者の膿塗抹標本では太鼓ばち状の芽胞を有する:C.tetani
・ ガス壊疽の膿塗抹標本では大きな車輌型(芽胞は確認できない):C.perfringens
通常,白血球はほとんど見られない。見られたとしても,その白血球の形はC.perfringens の毒素作用で歪められていることが多い。
・ 先細りの痩せたグラム陰性桿菌(紡錘形):F.nucleatum
・ グラム陰性小球菌(グラム陽性に染まる傾向にある):Veillonella spp..
・ グラム陰性球桿菌:Porohylomonas spp. Prevotella spp..
・ グラム陽性フィラメント状菌:Actinomyces spp.
・ グラム不定わん曲:Mobiluncus sp.
*嫌気性菌の形態学的な推定から分離培地を選択することにより,同定検査を速やかに実施することができる。
● 起炎菌決定に適した検査材料の採取,輸送及び処理
嫌気性菌の検出率は検体の採取法,採取量及び輸送法により異ってくる。分離率を上げるためには,空気との接触を避けて検体を採取し,速やかに輸送(保存)しなければならない。臨床検査室は,検体を肉眼的に観察して,適切な検体か否かを判別することが重要である。不適切な検体と判断された場合(常在菌や汚染菌の混入)は再度検体の採取を依頼することも必要となる。常在菌や汚染菌の混入を避けるために十分消毒した後,できる限り滅菌綿棒(スワブ)を使用せず,針とシリンジで採取する。吸引物(脳脊髄液,関節液,胸水,膿傷)や,手術時に無菌的に採取した感染組織材料を対象とする。輸送には嫌気性菌輸送培地(嫌気ポ−タ−)を使用した場合は,採取後2時間以内,滅菌容器或いは滅菌試験管を使用した場合は30分以内に検査室に届いていることを確認する。また検査材料の採取した時間を記載してもらうことも重要である。検査室では,材料の培地への接種はできれば嫌気性環境下で行うようにしたい。『嫌気チェンバ−法』は検体処理に関するすべてのステップを酸素のない嫌気性環境で行うことができる。『嫌気ジャ−法,嫌気バック法』は大気中で材料の処理及び培地への塗抹作業が(大気暴露時間)30分以内を目安にして可能な限り迅速に行う必要がある。
● 嫌気性菌検査に用いる培地
1) 非選択培地 :ブルセラHK(RS)血液寒天培地,アネロ・コロンビア血液寒天培地ABHK寒天培地など
2) 選択培地 :PVブルセラHK血液寒天培地,PV加ABHK寒天培地,PEA加ブルセラHK血液寒天培地,BBE寒天培地CCMA(CCFA)寒天培地,変法FM培地,Egg Yolk(卵黄加寒天培地)
3) 増菌培地 :GAM半流動高層培地,ブルセラHK半流動高層培地など
非選択培地(ブルセラHK(RS)血液寒天培地):ビタミンK1,ヘミンを含み,嫌気性菌全般の分離培養に適している。ヒツジ脱繊維血液の併用により,C.perfringensの逆CAMPテスト,Mobiluncus sp.のスクリ−ニング及び同定キットの前培養にも適している。
選択培地(PV加ブルセラHK寒天培地(ウサギ)):Bacteroides spp. Prevotella spp.やF.nucleatumなどの胆汁感受性菌種の選択分離に適している。
選択培地(BBE寒天培地):B.fragilis groupの選択分離及び,鑑別用培地である。
20%胆汁に感受性菌は抑制され,集落周辺の黒変により,エスクリン加水分解能を観察することができる。B.fragilis group以外にもF.varium, F.mortiferum及びBiopila wadsworthia は20%胆汁及びゲンタマイシンに耐性であるため発育する。
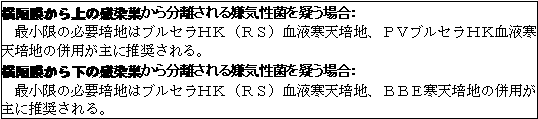
● 培養時間
嫌気チェンバ−法:嫌気性グロ−ブボックス内の孵卵器で培養した場合,2日で嫌気性菌の多くを確認することができる。しかし,嫌気ジャ−や嫌気バックを用いる場合には,3日は待って観察するのが良い。使用した培地の質や酸素暴露時間,培養環境などにより異なるが,B.fragilis groupが十分に発育するには,1〜2日,B. urealyticus group, Fusobacterium spp. Veillonella spp.では2〜3日,Porphyromonas spp.では3日,Actinomyces spp. B.wadsworthiaでは5〜7日が必要である。従って,嫌気培養は3日培養では検出率が60%以下であるため,5〜7日まで培養を継続する必要がある。
● 検査材料別の重要度
嫌気培養の対象とする検体は常在菌或いは汚染が少ないものでなければならない。
嫌気性菌検出には材料別に重要度を以下のカテゴリ−別に分類し培養検査を進める。
嫌気培養の対象となるカテゴリ−Aと通常は嫌気培養の対象とならないが,場合によっては嫌気培養が行われることがあるカテゴリ−Bとに分類する。さらに前者を検体中に存在する重要度の高い菌種を効率よく分離するために,さらにA-1からA-3の3つに分類する。
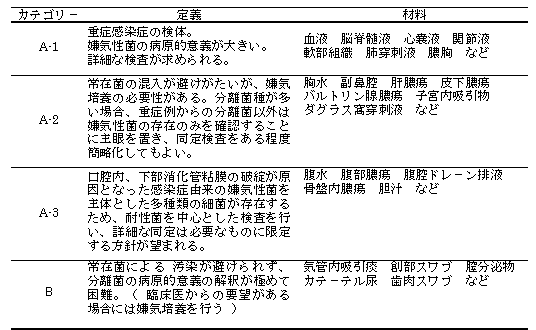
● 細菌性誤嚥性肺炎について
嚥下機能は加齢とともに低下することが知られているが,一方,年齢に関係なく嚥下機能の低下をきたしやすいアルコ−ル依存症,胃切除,脳血管障害,口腔外科領域或いは耳鼻咽喉科領域の腫瘍摘出などの素地を有する場合には,誤嚥が肺炎の原因となることを疑う必要がある。誤嚥性肺炎の起炎菌は市中肺炎の場合と同様,肺炎球菌,インフルエンザ菌,黄色ブドウ球菌に加え,嫌気性菌をはじめとする口腔内常在菌の関与にも考慮する必要がある。通常,肺炎の起炎菌決定は喀痰培養によって行われるが,喀痰には上気道常在菌の混入が避けられず,正確な起炎菌や嫌気性菌の関与を推測することは困難である。そのため肺炎の病態を明らかにする目的で,経気管吸引法(TTA)や経皮的肺穿刺吸引法があるが,「誤嚥性肺炎では嫌気性菌が関与するものとして嫌気培養は必要としないことを臨床医にコメントすべきである」また治療はβ−ラクタマ−ゼ阻害剤( ABPC / SBT ),CLDMの併用療法を推奨している。
● 抗菌薬関連下痢症について
多くの下痢症原因の中で,抗菌薬投与経過中に発症する特異な菌種で抗菌薬関連腸炎・下痢症と言われる。C. difficileは長期入院患者における大腸の偽膜性腸炎や抗生物質に関連した下痢症(C.difficile-associated diarrhea:CDAD)として臨床上重要である。芽胞を有するため病院環境に長期わたって存在し,院内感染原因菌として注目されている。糞便と共に腸管から排泄されるC.difficile は,医療従事者の手指などを介して患者間で頻繁に伝播すると言われる。予防対策としては,患者接触における手袋の着用,接触前後の手洗い,環境の念入りな湿式清掃などの対策が必要である。
米国では多くの院内感染例が報告されているが,日本では適切な臨床診断及び検査が行われていないことが多いので,感染の実態は不明である。最近,日本の病院におけるToxinA(−)ToxinB(+)株による院内集団発生事例が報告された。ToxinA(−),B(+)株が分離された症例では優位に頻繁に抗癌剤が使用されていると報告されている。
臨床的にCDADが疑われる患者糞便中のToxinA(−)であっても消化管症状が改善しない場合や抗菌薬や抗癌剤投与の多い患者の場合はC.difficileの培養を行う必要がある。
院内集団発生が疑われた場合には,疫学的調査に菌株が必要であり培養検査が重要になる。
CDADは内視鏡的に大腸の偽膜性病変が確認されれば偽膜性大腸炎と診断される。 現在,臨床検査室で実施されているCDAD診断のための検査は,主に糞便検体からのToxinA検査及び培養検査である。嫌気培養は48時間以上の時間を要するため迅速診断に役立つとは言い難い。CDAD診断には内視鏡下で偽膜性病変を確認することが重要である。
また糞便検体を用いて短時間で結果が得られるToxinA検査の診断意義は高いとされている。このため,検査指示時,患者の病態,抗菌薬投与の有無,目標菌種など検査室に伝えないと,適切な微生物検査は行えないと考えられる。
C.difficileの培養法(芽胞選択)
糞便検体を純アルコ−ルで等量混合し,30分から1時間室温放置後,嫌気状態に還元しておいた血液添加培地またはCCF(M)A寒天培地に嫌気条件下で2〜5日間培養する。血液添加培地では,やや大きな辺縁不整の光沢のないラフ形コロニ−に着目し,紫外線を照射して黄緑色の蛍光が陽性の株について検査を進める。CCF(M)A寒天培地では,黄色のやや大きな辺縁不整のラフ形コロニ−について検査を進める。いずれの培地でも,馬小屋臭と呼ばれる特有の 悪臭は本菌の推定に極めて有用である。
( 芽胞の形成は選択培地よりも非選択培地に継代培養した方が良好である )
● 細菌性膣症と嫌気性菌の検査について
細菌性膣症(Bacterial Vaginosis,BV)は複数の膣内細菌の異常増殖と過酸化水素を産生するLactobacilli spp.の減少による,膣のエコシステムの重大な変化である。
BVの特徴は,(1)Lactobacilli属の減少ないし欠如,(2)Gardnerella vaginalis密度の上昇,及びClue cellの有無(3)Prevotella spp. Porphyromonas spp. Peptostreptococcus spp. Mobiluncus sp. などの嫌気性菌,及びMycoplasma spp.などの増加である。
* 細菌性膣症の治療にはCP膣錠のみ,他の抗菌薬は使用しないので,基本的に細菌性膣症の膣分泌物の嫌気性菌培養は実施しない代わりにNugent score(BVスコア)を用いてLactobacilli form, Gardnerella form及び,Mobiluncus form の菌量から検鏡しスコアリングしてコメントする。
* 細菌性膣症の検体,或いは上行性感染があるために膣分泌物で代用して提出された検体かを知っておく必要がある。
* 嫌気性菌Mobiluncus sp.の培養は,臨床的に必要ではない。
(グラム染色の検鏡で十分である)
* Nugent score(BVスコア)を普及させる必要がある。
● 嫌気性菌の同定レベル(レベル1a〜2b)
すべての菌の同定を菌種レベルで行う必要はないが,できるだけ菌群レベルまで整理する習慣が必要である。
レベル1a:グラム染色所見及び集落性状 から菌種を推定,
レベル1b:選択培地から菌種を推定。
レベル2a:同定キットを使用。
レベル2b:ガスクロマトグラフィ−を使用。
レベル2aは迅速同定キット(4時間後判定)が非常に簡便な方法であるが,非常に高価である。レベル2bのガスクロマトグラフィ−法は研究目的としては非常に有用ではあるが,検査室ではコストもかかるため,そこまで時間をかける必要性はないと考えられる。従って,レベル1a及び1bを用いて嫌気性菌の同定を簡略化する方向で進める。
● 推定同定に有用な性状及び検査法
a, グラム染色所見及び集落の観察(臭い,外観)など
b, 選択培地での発育性状(BBE寒天培地)
エスクリン分解(集落周囲黒色〜褐色:B.fragilis group ,F.mortiferum )
エスクリン非分解(無色集落:B.vulgalis,F.varium ),
(目玉様集落:B.wadsworthia )
c, UV照射下の蛍光発色(ブルセラHK寒天培地)
赤色レンガ色蛍光(Prevotella spp. Porphyromonas spp.),薄黄緑色蛍光(F.necrophorum, F.nucleatum), 赤色蛍光(C.ramosum) など
d, 簡易試験法
→Ryuの試験:
3%KOH水溶液を用いて糸引き現象を調べる方法
嫌気性菌の場合,グラム染色で陰性に染まるグラム陽性菌を鑑別するために用いられる。グラム陰性菌の外膜にあるLPSがKOHにより溶出する現象で,グラム陽性菌では厚いペプチドグリカン層のため溶出しない。
糸引き現象(+):グラム陰性,糸引き現象(−):グラム陽性菌と判定する
→カタラ−ゼ試験:
15%過酸化水素(3%でも可)を用いて過酸化水素を水と酸素に分解する酵素であるカタラ−ゼの産生の有無を調べる方法。
30秒以内に発泡が見られた場合陽性と判定する。ほとんどの嫌気性菌はカタラ−ゼ陰性であるが,Actinomyces spp.の数株,B.fragilis groupの数株は陽性,Propionibacterium acnes及びB.wadsworthiaは強陽性である。
→スポットインド−ル試験:
トリプトファンを含む培地(ブルセラHK寒天など)上のコロニ−を竹串で多めにとり,試薬を染み込ませた濾紙に塗布すると陽性は1分以内に青色に変色する。本試験は必ず純培養菌を使用すること。黒色集落を示すPrevotella spp. Porphyromonas spp.は反応の確認が困難なため,裏側から見ると陽性反応が確認できる。
→半流動高層培地での発育性:
純培養菌,或いは分離培地から嫌気/好気の有無,ガス産生及び運動性を確認するのに用いる。必ず嫌気性菌を疑う菌株の増菌用( 嫌気帯でのみ発育 )として用いる。
→酵素反応試験:
酵素と発色(光)酵素基質を利用した方法(RID Zyme)
発光または発色基質を用いるテストで,1種類の酵素が作用する方法のため,短時間で結果が得られる。純培養集落から1種類または数種類のテストを組み合わせることにより,簡便かつ迅速に鑑別することができる。
MαGLU-ANテスト
(菌のもつα-glucosidaseを検出:UVランプ照射により蛍光の有無を判定する)
ブルセラHK寒天培地に発育した黒色集落或いは黒色色素産生グラム陰性桿菌
↓
MαGLU-ANテスト
(+)↓ ↓(−)
Prevotella spp. Porhyromonas spp.
PRO-ANテスト
(菌のもつL-proline aminopeputidaseを検出する:発色液滴下により発色の有無を判定する)ブルセラHK寒天培地或いはCCFA寒天培地に発育したClostridium spp,
↓
PRO-ANテスト
(+)↓ ↓(−)
C.difficile(推定同定) Clostridium spp.
以上,述べたような方法を組み合わせることによって属レベルから,さらに種レベルにおける鑑別が可能になると考えられる。
● 嫌気性菌感染症の治療
近年,抗菌薬剤の多用の結果,各種の抗菌薬剤に耐性の嫌気性菌が増加してきている。この主因はβ-ラクタマ−ゼ産生菌の増加である。β-ラクタマ−ゼを産生する嫌気性菌はB.fragilis group, Prevotera spp. Porphylomonas spp. B.wadswarthia, Fusobacterium spp. C.ramonsum, C.clostridioform, C.butyricum などがある。
さらにB.fragilis group を代表とする嫌気性菌感染症の治療に推奨されてきたクリンダマイシン( CLDM )に耐性菌も増加しつつある。
嫌気性菌感染症の抗菌薬療法は Empiric therapyとして開始されるべきである。ほとんどの嫌気性菌感染症は好気性菌との混合感染であることが多いので,共存する好気性菌も目標とした抗菌薬療法が要求される。
B.fragilis group ではβ-ラクタマ−ゼ産生菌が多く,かつ多剤耐性菌も多いので,β-lactam剤/β-lactamase阻害剤との合剤が最適で,第一選択薬となる。カルバペネム系薬(IPM, MEPM)がこれに次ぐ。
● 嫌気性菌の選択薬剤
現在,臨床的に嫌気性菌の薬剤感受性検査の対象菌種はB.fragilis group, Prevotera.spp Porphyromonas spp. Fusobacterium spp. Clostridium spp. B. wadsworthiaなどである。感受性検査に加える薬剤は,β-lactam剤/β-lactamase阻害剤との合剤,カルバペネム系薬,クリンダマイシン,セファマイシン系薬,クロラムフェニコ−ル,嫌気性菌に括性のあるセファロスポリンなど。
● 嫌気性菌感受性試験法
E-テスト,微量液体希釈法があるがNCCLS法ではB.fragilis groupのみ精度管理ができないためPrevotella spp.などの測定には問題がある。現時点では,Prevotella spp.については,β-ラクタマ−ゼ産生性の有無を検査するだけでもよい( Prevotella spp.の50%以上がβ-lactamaseを産生する )。すべて検出された嫌気性菌についてあやふやな感受性デ−タ−を報告する必要はないし,それだけのエビデンスがなければ,必要性のある菌種に限定して感受性検査を実施すべきである。
(一例 : C.perfringensはアミノグリコシド系以外の多く抗菌薬に感受性を示すので,一般的には治療薬選択のための薬剤感受性検査は必要ないとされている )
● メタロ−β−ラクタマ−ゼ産生性 B. fragilis
B. fragilisの一部の株に,メタロ−β−ラクタマ−ゼを産生し,イミペネム(IPM)などのカルバペヌム系薬に耐性を獲得した株が存在することが報告された。
最近,我が国でも伝達性のカルバペネム系薬耐性を示すB.fragilis が報告されているが,カルバペネム系薬の使用頻度の高い我が国においては,IPM耐性B.fragilisについて注意していく必要がある。検査法はSMA法(メルカプト酢酸ナトリウム)或いは2MPA法(2−メルカプトプロピオン酸)のディスク拡散法(嫌気培養)に準ずる。
( 参考 )・・・・・・・
大阪医療センタ−で経験した血液培養陽性C.perfringens敗血症例
C. perfringensはウエルシュ菌とも呼ばれ,ガス壊疽或いは食中毒菌として知られているが,強い溶血毒{α−トキシン(phospholipase C), ノイラミダ−ゼ}を産生する。C.perfringens敗血症の診断は顕著なヘマトクリットの低下と強度の溶血がみられる。ヘマトクリットがゼロに近いような強い溶血を見た場合はC.perfringensをまず考えるべきである。このような状態の患者は悪性腫瘍などの基礎疾患を有しており,原因不明のショツク状態に陥っていることが多い。抹梢血塗抹標本でグラム陽性桿菌が観察されれば,本症が強く示唆される。本症例も血液培養管内で高度溶血及びガスの産生が認められた。この所見も診断上重要である。突然のショック状態の場合,本菌による敗血症も考慮し血液培養を勧めるべきである。また血液検査室には抹梢血のヘマトクリット異常低値と強度の溶血性がある場合C.perfringens敗血症を強く疑うことを連絡しておくことが必要である。
( おわりに )
近年,迅速微生物検査としてMRSA,多剤耐性グラム陰性桿菌及び結核菌など遺伝子検査法が進歩し,嫌気性菌のように培養に時間を要する検査は比較的軽視される傾向にある。特に,混合感染を疑う場合,臨床的に重要な嫌気性菌を見逃しているケ−スが多いようである。当院でのC.perfringens敗血症例においても嫌気性菌感染症は重篤な感染症で微生物検査技師の技術力が救命に及ぼす影響は非常に大きいと考えられる。今回の勉強会では,嫌気性菌の検査法及び臨床的意義について,さらに深く取り組まなければならないと痛感しました。