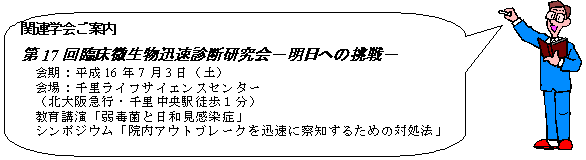・ マスク,手洗いの励行
・ ワクチンはまだ実用化されていない
・ 薬剤耐性菌はマクロライド系に高度耐性のものが日本でも報告があり,EMに耐性のものは,その他のマクロライド系やリンコマイシン系に交叉耐性を示す。耐性機序は23S rRNAのPoint mutationによってタンパク合成系の変異により作用点を変異させるものと考えられる。
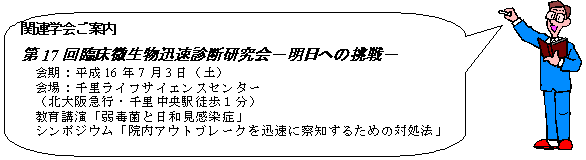
感染症レビュー
〜Mycoplasma pneumoniae〜
結核予防会大阪病院 伏脇 猛司
| 分類・特徴 |
・ Molicutes 綱 Myoplasama 属
・ 1944年Eatonらが異型肺炎患者より分離しウイルス様病原体とし,1962年Chanockらが無細胞人工培地での増殖に成功
・ 0.2〜3μmの大きさで光学顕微鏡では菌体は観察できない
・ 細胞壁を持たない為,細胞壁合成阻害剤は無効
・ 近縁の菌としてAcholeplasma(ごくまれにヒトに日和見感染),Phytoplasma(植物の病原菌,昆虫が媒介),Ureaplasma(U.
urealyticumはヒトの泌尿生殖器感染)などがあり,また同じMyoplasama 属のM. hominis, M. genitalisもヒトの泌尿生殖器感染を起こす。
Mycoplasma oraleとMycoplasma salivariumはヒトの口腔内常在菌。
M. mycoides(牛肺疫菌),M. agalactiae(ヒツジやヤギの乳房炎),M. gallisepticum(ニワトリの呼吸器感染)などがある。
・ コレステロール合成能が無い為,培養にはコレステロールと長鎖脂肪酸を要求する
| 感染経路 |
・ 飛沫感染
・ 家庭や学校など閉鎖された環境において経気道感染することが多い
・ 線毛上皮細胞に接着・増殖し,その細胞を障害して線毛運動を阻害し,さらには線毛上皮細胞を脱落させ感染病巣を拡大させる
| 潜伏期間 |
・ 2〜3週間
| 好発年齢 |
・ 6〜8歳がピークで幼児期から青年期が多いが,発症は全年齢で起こる
| 周期性 |
・ 以前はオリンピックの年に流行がみられたが,近年ではその周期性はみられない
| 症状 |
・ 発熱(38℃前後),全身倦怠,頭痛,長く続く乾性咳嗽(夜間や朝方に多い)
・ 合併症として中耳炎,副鼻腔炎,鼓膜炎などがみられ,まれに髄膜炎,Guillain-Barre症候群などがみられる
| 検査所見 |
・ 胸部X線では,片側の下肺野に異型肺炎像がみられることが多く,典型例ではすりガラス様の淡い陰影がみられる
・ 寒冷凝集反応が陽性になるのは50%程度
・ CRP上昇
・ WBC軽度上昇
・ Chlamydia肺炎,Legionella肺炎,ウイルス性肺炎などの異型肺炎との鑑別が必要
| 診断 |
・ 培養: PPLO培地,Mycoplasma培地などの基礎培地をオートクレーブ後に酢酸タリウム,ペニシリンG,ろ過滅菌したウマ血清を添加する。
咽頭粘液などの患者検体を上記培地(液体:増菌,寒天:分離)に接種し,1週間後に寒天培地を観察,増菌培地は寒天培地に接種し,さらに1週間培養した後観察する。
直径1mm程度のコロニーがみられれば顕微鏡にてコロニー性状を観察する。
口腔内常在菌であるMycoplasma oraleとの鑑別が必要で,コロニー性状,赤血球吸着能,溶血能,蛍光抗体法などにより鑑別を行う。
・ 血清学的診断:補体結合反応(CF),間接赤血球凝集反応(IHA)にて,ペア血清で4倍以上の上昇で陽性。単一血清では,CF で64倍以上,IHA で320倍以上の抗体価があれば陽性。また粒子凝集法(PA),蛍光抗体法(IF),酵素抗体法(ELISA)によってIgM,IgG抗体を検出する方法もある。
ただし,発症2週間未満では抗体価が上昇していない場合がある為,早期の迅速診断とはならない。
近年PCR法やDNAプローブ法が開発され早期迅速診断に期待される。
| 治療 |
・ 細胞壁合成阻害剤は無効
・ 治療にはテトラサイクリン系,マクロライド系が用いられる
| 感染対策 |
・ 各種消毒薬や加熱には比較的弱い
・ マスク,手洗いの励行
・ ワクチンはまだ実用化されていない
・ 薬剤耐性菌はマクロライド系に高度耐性のものが日本でも報告があり,EMに耐性のものは,その他のマクロライド系やリンコマイシン系に交叉耐性を示す。耐性機序は23S rRNAのPoint mutationによってタンパク合成系の変異により作用点を変異させるものと考えられる。