堛椕偵峷專偱偒傞姶愼徢旝惗暔専嵏偲偦偺庢傝慻傒曽
乣晅壛壙抣偺偁傞寢壥曬崘傪偡傞偨傔偺曽朄偲
堾撪姶愼杊巭妶摦偵娭傢傞偨傔偺忣曬偲傾僾儘乕僠乣
嵿抍朄恖嶃戝旝惗暔昦尋媶夛丂嶁杮丂夒巕

丂杮擭搙偺掕婜島廗夛偱偼'晅壛壙抣傪傕偭偨専嵏幒傪傔偞偟偰'傪憤崌僥乕儅偲偟偰婇夋偟偰傒傑偟偨丅晅壛壙抣偲偄偭偰傕條乆偱偡偑丆捠傝堦曊偺専懱専嵏丆婡夿揑偵寢壥傪曬崘偡傞偩偗偺専嵏幒偱偼側偔丆堛椕?椪彴偵栶棫偮専嵏偺偱偒傞専嵏幒丆偦偺偨傔偺晅壛壙抣傪傕偭偨専嵏幒偑昁梫偲偝傟偰偄傑偡丅偦偺傛偆側僯乕僘偵摎偊傞偨傔偵偼偳偺傛偆側偙偲偑偱偒傞偺偐丆愝旛傗梊嶼偺惍偭偨巤愝偱側偔偰傕偱偒傞偙偲偼偁傞偼偢偱偡丅偦傟偼壗偐傪扵傝丆戞堦曕傪摜傒弌偡堦彆偲側傟偽偲巚偄傑偡丅
丂暯惉16擭4寧27擔乮壩乯偵戞1夞掕婜島廗夛偲偟偰戝嶃晎棫媫惈婜丒憤崌堛椕僙儞僞乕椪彴専嵏壢姶愼徢旝惗暔専嵏丂徏壀丂婌旤巕丂愭惗偵乽堛椕偵峷專偱偒傞姶愼徢旝惗暔専嵏偲偦偺庢傝慻傒曽亅晅壛壙抣偺偁傞寢壥曬崘傪偡傞偨傔偺曽朄偲堾撪姶愼杊巭妶摦偵娭傢傞偨傔偺忣曬偲傾僾儘乕僠乿偲戣偟偰屼島墘偄偨偩偒傑偟偨丅忢偵椪彴偵栶棫偮専嵏傪捛媮偝傟偰偙傜傟偨徏壀愭惗偵丆擔忢嬈柋偺側偐偱偳偺傛偆側偙偲傪偝傟偰偄傞偺偐屼島墘捀偒丆埲壓偵偦偺撪梕傪曬崘偟傑偡丅
椪彴堛偑抦傝偨偄乽姶愼徢専嵏忣曬乿
丂堛巘偼壗傪抦傝偨偄偺偐丆暦偒偨偄偗偳暦偗側偄偲偄偆堛巘偺媈栤傪媯傒庢偭偰丆専嵏幒偐傜堛巘偺抦傝偨偄偙偲傪採帵偟偰偁偘傞偺偑嵟傕椙偄専嵏偱偁傝丆埲壓偵変乆偑擔崰幚巤偟偰偄傞曽朄傪徯夘偡傞丅
1. 姶愼徢旝惗暔専嵏偵揔偟偨専懱偲偼丠
仜 専懱嵦庢朄
仜 専懱昳幙偲偦偺椪彴揑堄媊
丂嘆 歕醾偺嵦傝曽偲擏娽揑昳幙娗棟偵偮偄偰丆梊傔専懱嵦庢帪偺夝愢帒椏乮嵦庢慜偵偆偑偄傪偡傞丆嵦庢帪偺拲堄帠崁丆専懱偺斃憲偲曐懚偵娭偡傞拲堄帠崁乯傪奺姵幰偲昦搹丆奜棃偵攝晍偟偰偍偔丅
丂嘇 専嵏寢壥曬崘偵Miller-Jones暘椶偵傛傞専懱乮歕弌歕醾乯偺昳幙昡壙偲Geckler偺暘椶乮歕醾丆堲摢乯傪偦偺堄媊乮夝愢乯偲暪偣偰曬崘偡傞丅乮嶲峫1乯
亙嶲峫1亜
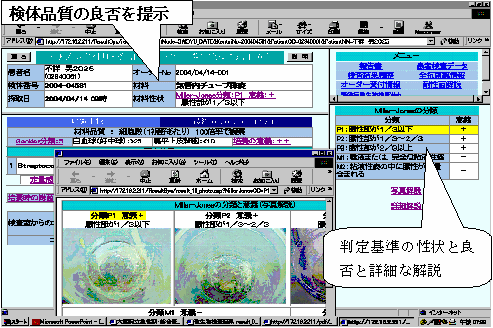
2丏専嬀帪偺嬠検偲妱崌丆攟梴帪偺嬠検偲妱崌
丂嬀専偍傛傃攟梴偺嬠検昞帵偵偮偄偰妱崌偲夝愢傪偡傞丅嬀専偱尒偊偰偨嬠偺宍傪僀儔僗僩採帵偡傞偙偲偵傛偭偰堛巘偑捈愙専嬀偡傞偲偒偵栶棫偮丅偙傟偐傜偼堛巘偑捈愙揾枙昗杮傪専嬀偟偰恌抐偡傞帪戙偵側傞偺偱丆偦偺墖彆偲側傞丅乮嶲峫2乯
亙嶲峫2亜

3丏恦懍専嵏朄傗娙堈朄偺姶搙丒摿堎惈偺昞帵
丂恦懍専嵏朄丆娙堈朄偺寢壥傪梲惈丒堿惈偲曬崘偡傞偑丆偦偺寢壥傪偳偙傑偱怣梡偟偰傛偄偺偐丆偦傟偵偮偄偰姶搙丒摿堎搙傪摨帪偵昞帵偡傞丅偦偺寢壥丆嵞専嵏傪幚巤偟偨傝懠偺専嵏僨乕僞偲徠崌偟偨傝敾抐嵽椏傪採嫙偡傞偙偲偑偱偒傞丅乮嶲峫3乯
丂傑偨丆傢偐傝傗偡偄昞尰偱岆夝傪彽偐側偄専嵏寢壥偺曬崘偺巇曽丒夝愢傪岺晇偟側偗傟偽側傜側偄丅
亙嶲峫3亜
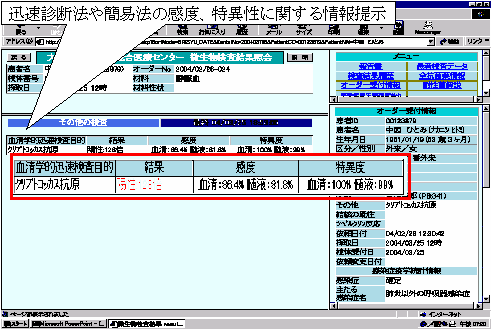
4丏姶愼徢帯椕偵懄墳偟偨栻嵻姶庴惈寢壥偺採帵丒懴惈忦審偵傛傞栻嵻姶庴惈傪峣傝崬傓
丂2擔娫攟梴偟丆72悽戙乛擔丆2擔娫偱144悽戙岎戙偟偨嬠偺姶庴惈帋尡傪偟偨偲偙傠偱尦偺僨乕僞偲偼偄偊側偄丅偟偐偟丆尰帪偱偼専嵏偺尷奅偐傜巇曽偺側偄偙偲偱偁傞偑丆尷奅偑偁傟偽偦傟傪曗惓偡傟偽傛偄傢偗偱丆惗僨乕僞傪傑偢弌偟偰丆偦偺拞偐傜椪彴偵巊偊傞傛偆側忦審偵曄偊傞丅乮嶲峫4乯
丂栻嵻姶庴惈専嵏偼巊偊傞栻嵻傪挷傋傞偺偱偼側偔丆巊偊側偄栻傪挷傋偰偄傞丅栻嵻姶庴惈専嵏偱偼105屄偺嬠偟偐愙庬偟偰偄側偄丅姶愼昦憙偺嬠検傕晄柧偱丆姶愼昦憙偵栻嵻偑摓払偡傞偐偳偆偐傕傢偐傜偢丆帋尡娗撪偱専嵏偟偰偄傞偩偗偱丆姶庴惈偩偐傜丆傑偨MIC偑掅偄偐傜偲偄偭偰偦偺栻偑岠偔偲偼尷傜側偄丅偟偐偟懴惈偱偁傟偽憻婍堏峴偵偐偐傢傜偢懴惈偼娫堘偄側偔岠偐側偄偲偄偆偙偲偱偁傞偑丆姶庴惈偼偦偺栻偑巊偊傞栻偲偼尷傜側偄丅偦偆偡傞偲144悽戙岎戙偟偰偄傞嬠偺姶庴惈僨乕僞偱偼傕偲傕偲偺姶庴惈昦懺偑曐偨傟偰偄傞傕偺偱偼側偄丅堚揱巕偵慻傒崬傑傟偰偄傞傕偺偱側偗傟偽扙棊偡傞偙偲偑偁傞偺偱丆偦偺帪偵僨乕僞傪曗惓偟側偗傟偽側傜側偄丅椺偊偽NCCLS偱Enterococcus spp.偼傾儈僲僌儕僐僔僪宯丆僙僼僃儉宯丆僋儕儞僟儅僀僔儞丆ST崌嵻偼寢壥偲偟偰昞帵偟偰偼側傜側偄偲偄偆偙偲偑尵傢傟偰偄傞偑丆乽仜仜仜偼椪彴揑偵帯椕岠壥偑婜懸偱偒傑偣傫乿偲偄偆昞尰偱峣傝崬傫偱偄傞丅暪偣偰峣崬傒忦審傪帵偟偰丆姶庴惈寢壥傪昞帵偟側偄偙偲傪曬崘偡傞丅兝儔僋僞儅乕僛偼僾儔僗儈僪惈偵嶻惗偝傟傞傕偺偑懡偔丆栻嵻偺巋寖偑側偔側傞偲兝儔僋僞儅乕僛堚揱巕傪嶌傞偺傪巭傔偰偟傑偆偺偱72悽戙岎戙偟偨偲偙傠偱偼兝儔僋僞儅乕僛傪嶻惗偟側偔側偭偰偄傞応崌偑偁傞丅偦偺偲偒偼兝儔僋僞儅乕僛偼嶻惗偝傟偰偄傞偑儁僯僔儕儞丆僙僼僃儉偼姶庴惈偱偁傝寢壥偑夝棧偡傞傛偆側偙偲偵側傞丅偙偺傛偆側応崌偼兝儔僋僞儅乕僛偺忦審偵傛傝峣傝崬傫偱儁僯僔儕儞丆僙僼僃儉丆僇儖僶儁僱儉偼巊梡偱偒側偄偙偲傪昞尰偡傞丅
丂嬠偑専弌偝傟偨専懱偑壗偱偁傞丆偳偺栻嵻偑憻婍堏峴偑椙偄偐偲偄偆偙偲偐傜帯椕偑巒傑傞偺偱丆憻婍堏峴偵偮偄偰丆巊梡偱偒側偄姵幰偵娭偡傞嬛婖丆暃嶌梡偺忣曬傪偄偮偱傕採嫙偱偒傞傛偆偵弨旛偟偰偍偔丅
亙嶲峫4亜
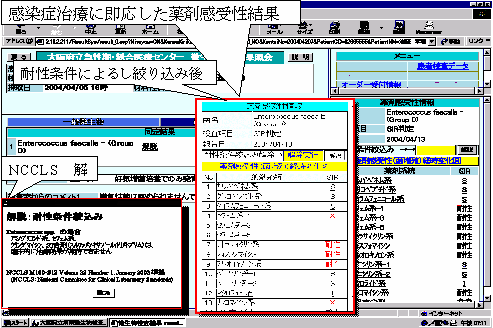
5丏専弌嬠偺帯椕忋偺摿挜偲専懱昳幙偺夝愢
丂専弌嬠偺夝庍偵偮偄偰専懱昳幙偐傜専懱偺嵞採弌偑朷傑偟偄応崌偼丆専嵏幒偐傜専懱偺嵞採弌傪採埬偡傞丅傑偨丆挵娗宯姶愼徢偱偼丆偦偺帯椕偵偍偗傞壔妛椕朄偵娭偟偰挵撪嵶嬠偦偆偺夵慞傪採埬偡傞偙偲傕偁傞丅
6丏曬崘撪梕偺昳幙娗棟偲昳幙曐徹
丂巗斕帋栻攟抧偵偮偄偰惢憿儊乕僇乕偺昳幙帋尡惉愌彂傪擖庤曐娗偡傞丅昳幙娗棟偑廫暘偵偝傟偨帋栻攟抧傪巊梡偡傞偙偲偑婎杮偱偁傞丅
7丏塽妛摑寁偺婎偵側傞専嵏僨乕僞偼丆椙昳幙偺寢壥偩偗傪懳徾偵廤寁丒夝愅偡傞丅
丂埆昳幙偺専懱偺専嵏寢壥傪娷傔偨塽妛摑寁偼娫堘偭偨忣曬傪傕偨傜偡丅
丂椺偊偽姶庴惈専嵏偵偮偄偰偼忢偵愙庬嬠検丆扨撈嬠偱偁傞偙偲傪僠僃僢僋偡傞偙偲偐傜姶庴惈専嵏寢壥偺昳幙曐徹傪峴偄丆偮傑傝偼怣棅惈偺崅偄椙昳幙偺寢壥偱偁傞偙偲傪妋擣偟偰丆塽妛摑寁偺婎慴偲傕偡傞丅
8丏椪彴傊偺姶愼徢旝惗暔専嵏幒偺栶妱
丂壗傪偡傞傋偒偐丠乗姶愼徢帯椕偲堾撪姶愼奼戝杊巭傊偺峷專
丂丂乮1乯寢壥偺恦懍曬崘
丂丂乮2乯懴惈嬠暘棧丒敪惗帪偺恦懍曬崘
丂丂乮3乯堾撪姶愼梊挍偺恦懍曬崘
丂丂乮4乯姶愼徢塽妛僨乕僞偺採嫙偲嫟桳
丂丂乮5乯姶愼徢塽妛摑寁僨乕僞偺採嫙偲嫟桳
丂丂乮6乯堾撪姶愼杊巭妶摦傊偺嶲壛
丂晹壆偑側偄偐傜偱偒側偄丆暔偑側偄偐傜偱偒側偄丆拠娫偵偄傟偰偔傟側偄偐傜偱偒側偄丒丒丒丒傗傞婥偑偁傞偐偳偆偐偱丆傗傞婥偑偁傟偽壗偱傕偱偒傞丅抧摴側搘椡丆壗偐傪偡傟偽壗偐偟傜偺惉壥偑尰傟傞丅
偍傢傝偵
丂忢偵"専懱専嵏偱偼側偔姵幰専嵏傪丆椪彴偵峷專偱偒傞専嵏傪"傔偞偝傟傞徏壀愭惗偺偛島墘偱偟偨丅戝嶃晎棫媫惈婜丒憤崌堛椕僙儞僞乕偩偐傜偱偼側偔丆変乆偺傗傞婥偝偊偁傟偽壗偐偱偒傞偙偲偑偁傞偼偢偱偡丅峏偵崱擔偱偼曋棙側偍彆偗僌僢僘偑廫暘偵偁傞帪戙偱偡丅偙偺傛偆側帪戙偵変乆偑"偱偒側偄"偲偄偆偙偲偼変乆偺懹枬偱偟偐偁傝傑偣傫丅崱擔偐傜丆峏側傞堦曕傪摜傒弌偟偰乽偆偪偺姶愼徢専嵏幒丒旝惗暔専嵏幒偼傎傫偲偆偵傛偔傗偭偰偔傟傞傛丅姵幰偝傫傛偔側偭偨傛丅偍堿偱姶愼奼戝偣偢偵杊偖偙偲偑偱偒偨傛丅奜拲傕偄偄偗偳丆旝惗暔専嵏偼堾撪専嵏偱傛偐偭偨傛丅乿偲偄偆惡傪暦偗傟偽丆変乆偺擔乆偺搘椡偑彮偟曬傢傟傞婥偑偟傑偡丅