2月定期講習会参加レポート
「微生物検査における教育のキーポイント」
- プロになるためには?プロを育てるには? -
大阪市保健所 保健医療対策課 堂園 昌隆
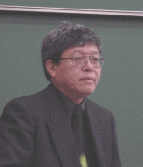
去る2月17日(火),大阪市立大学医学部4階中講義室において国家公務員共済組合連合会大手前病院 山中
喜代治先生をお迎えして,「微生物検査における教育のキーポイント-プロになるためには?プロを育てるには?」と題して御講演頂きました。以下に,当日の講演内容について報告致します。
(はじめに)
現在の臨床検査技師の学校教育において,基礎実習,病院実習をこなし,国家試験だけのために,ただ単純に技師を輩出するだけではプロを育てることはできない。
最近は,患者の診断を簡単にできる方法が多く出てきて,菌を分離培養しなくても良くなった。しかし,微生物検査のヒストリーは分離培養したコロニーから作られていく。
分離(isolation):材料から菌を取り出すこと
培養(culture):養い育てること
菌株(strain):1個の細胞から分化し,原則的に親細胞と同じ遺伝形質を備えた子孫の集団であり,これを保存した状態
(注)保存したものには菌株No.や患者名等他の培養物と見分けるためのの表示があること。表示のないものは菌株とは言わない。
同定(identification):未知の菌株の性状と既知菌種の性状が一致すること
分類(classification):相互関係を基に,菌株の類似性を整理すること
命名(nomenclature):国際細菌規約に則って学名を与えること
(分類の手法)
1970年以前はエネルギーの獲得方法により,5つの界Kingdom(原核生物・植物界・動物界・真菌・原生動物)に分類されていたが,1980年以降はリボゾームRNAの配列で大きく3つ(真正細菌・古細菌・真核生物)に分類されている。

(新菌種について)
普段の日常でも性状表を見ながらこれは多分,〇〇〇菌だろうといった名前の判らない菌株が出てくると思うが,新しい菌種が確定するまでには
① 同定不能の菌株は,多数の同様の株を集め詳細に分析する。
② その結果が1つの種を構成するかどうかを判断する。
③ 他の菌種と比べ明らかな差(リボゾームRNAの配列等)が認められる。
④ その菌株群に新しい菌種名の提案が考慮される。
⑤ これらの成績をIJSEMに公表する。
⑥ 原著者は基準株Type strainを指定する
(多数の株の中から最もスタンダードなものをType strainとする)。
⑦ 最低でも2ヶ所の異なる国の保存機関に登録する
⑧ IJSEMで約1年間異論がなければ確定する。
(IJSEM:International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology)
1 基準株とは
① その種の命名記載者が分離した菌株。
② 原著記載の性状を備えた純培養物。
③ 恒久的公共の菌株保存機関に預ける(ATCCなど)。
④ 他の研究者が利用できるよう義務付けられている。
⑤ 種名が存在する限りその名を担う。
⑥ 原著者がType strainを指定しなかった場合や消滅してしまった場合は,後の研究者が最適な株を選び新基準株(neotype)とする。
⑦ すべてが標準(standard)とは限らない。
2 IJSEMでの公表
理想としてはIJSEMに掲載し新菌種を公表すべきであるが,都合で掲載できなかった場合は他の雑誌に投稿し,そのコピーをIJSEMのeditorial officeに提案する。IJSEMはvalidation listを作って掲載し,約1年間おいて反論を待つが,同時掲載で異なる菌種の提案の例もある。(例えばMoraxella とBranhamella のように同じ号の隣接ページに掲載されているものもある。専門家によればMoraxella の方が先であろうとのこと。)
3 命名と基準種の問題
命名と基準種には不一致のものがよくある。例えば,Pseudomonadaceaeの基準種がPseudomonas aeruginosaであるように本来,基準種名がFamilyネームに使われるべきであるが,腸内細菌科(Enterobacteriaceae)の基準種はEnterobacterではなくEscherichia であり,これは命名委員会が規約を無視した結果である。また,ShigellaはEscherichiaと遺伝子学的に同一であり,本来はShigellaをEscherichiaの種とすべきであるが,病原性(病名)や疫学上では浸透しているので名前を変えるのは困難である。しかし近い将来,赤痢菌はEscherichia と呼ぶことになるであろう。
(院内検査とアウトソーシングについて)
"臨床検査は必要だが,臨床検査技師は必要ない"
中小の病院ではアウトソーシング(外注)が日常化し,大病院でも特殊検査は外注で済ませている。
外注検査機関の精度向上とネットワークの整備により,外注検査は迅速正確な検査報告も可能となり,院内検査と外注検査の迅速性の違いは検体送付時間位で,検査実施報告時間は院内検査も外注検査も殆ど変わらなくなっている。
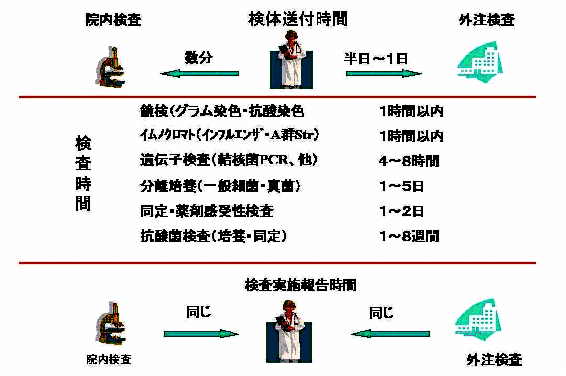
経済性が考慮されるあまり,外注万能主義が誇張されている傾向があるものの,技師側も真摯に受け止め,院内検査のメリットをそれぞれの施設の特殊性に応じて考えるべきである。そしてソフト面でも,院内検査に関わる技師として,
・ 病態管理:もっと患者を見ること。
・ 精度管理:検査機器や検査成績の管理だけでなく,患者管理をすること。
(カルテをDrと共に見て,こういう薬を使っているからこの検査項目の結果に影響していると考えられると言えるようにならないといけない。)
・ 一患者一技師:主治医が24h体制で患者を診るように検査技師もそうあるべき。
・ 経済観念:自分がやっている検査にいくらかかっているかの収支くらいは把握しておくこと。
等が,検査技師のプロスタイルである。
(プロとは何かについて)
江戸後期の浮世絵師,葛飾北斎は89歳の臨終の際,「あと5年生きられれば本当の浮世絵師になれるのだが・・・」と89歳にしてまだ自分はプロではないと言ったそうだが,プロとは何かについて触れたい。
§プロになるためには
1 目的・目標を立てること。
(学会発表等,何か目標を立てる)
2 完璧であること。
(完璧な仕事のための基礎トレーニングは隠れて行う)
3 ハプニングに動じないこと。
4 最後まで責任を果たすこと。
5 常に仕事のことを念頭に置くこと。
(休みに職場に出かけると普段気が付かなかったことが発見できる)
6 仕事が趣味であってはならない。
§プロになれない人
・楽な仕事しかしない人
(培地作りはいや。検体処理はいや。コロニーをみるだけ。)
・マニュアルがないとできない人
(言われたこと,書いてある通りにしかできない。何かトラブルがあるとすぐにメーカーに電話する。)
・ミスを恐れる人
(偽陽性や偽陰性の出やすい検査はいや。)
・すぐに成果を求める人
(主任になりたい。会長になりたい。)
・趣味でやっている人
(好きな時に好きなことを好きなようにやる。)
(私の秘訣)
最後に,私(山中)自身がこれまでに実感してきた病院に勤務するにあたっての秘訣について述べたいと思う。
1.患者様には愛をもって笑顔で接すること
※診察や検査の時だけでなく,待合室やエレベーター等,普段から患者に笑顔で話し掛けることが大切。
2.検査に対して最後まで責任を持つこと
※もし検査の手続きがまずくて患者を待たせたりしたのであれば,患者と接する医師や看護師に謝罪させるのではなく,検査技師に謝罪させる。
3.事務所と親しくすること
※ただ単に懇親にするということではなく,仕事を通じて信頼し合えるように努めること。(事務所から依頼された仕事は期限までではなく,迅速にこなす等)
4.緊張と緩和をもつこと
※緊張の緩和ではない。仕事中は常に緊張を持ってあたる。
5.あとはすべて運である
※人事を尽くして天命を待つ。
(講演の感想)
GLP(Good Laboratory Practice :検査実施適正基準)の導入により,検査に関する全ての作業が文章化され,全てのデータ,経過の記録,作業上のミスが細かくチェックされることで,某ハンバーガーショップのように,新人のアルバイトでもマニュアル通りにやれば一定水準の検査成績が出せる(逆に言えば同じ結果しか出せない)ようになった。特に管理者にとっては検査における信頼性を確保するシステムとしてGLPを決して否定するものではないが,講演にもあったように,GLPによるマニュアル検査をこなしているだけではプロにはなれないであろう。今回の講演を通じて,仕事に対する責任感や熱意・創造力といった今後の検査技師に必要な資質について改めて認識することができたと思う。